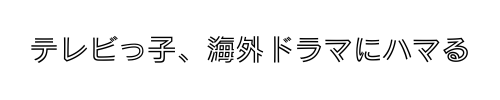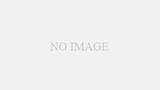岩殿城攻略レポート|壮絶な山城体験とその歴史
岩殿城は、山梨県大月市に位置する戦国時代の山城であり、かつて武田家の有力家臣・小山田氏が拠点としたことで知られています。今回は、実際に岩殿城を訪れた体験と、その歴史について紹介します。
岩殿城のアクセスと登山情報
駐車場情報(2025年2月22日現在)
- 市営駐車場:畑倉登山口まで約1.6km
- 畑倉登山口駐車場:約5台収容可能
- 岩殿山公園駐車場:国道139号線高月橋北側に位置し、11台分の駐車スペースあり
登山口の状況
浅利登山口と畑倉登山口以外は、土砂崩れや落石のため通行止め。特に冬季は氷が張ることがあるため注意が必要です。
2月22日時点で登山口付近の山肌に氷が張っていました。登山前に最新情報を確認してください。
過去最難関の山城?

kusariba
稚子落しルートは要注意!
- 尾根づたいに進むため、常にアップダウンが続く
- 道中に遺構はほぼ見当たらず、どこを進んでいるのか分からなくなる
- 滑りやすい土質のため、登山靴や装備が必須
- 山頂直前には鎖場あり、初心者には危険
- 山頂の岩殿城案内板にある簡易的な縄張り図が分かりづらい。大手門の場所が分からず間違って稚子落しルートに向かってしまった。
岩殿城の歴史

築城と城の特徴
- 築城時期:14世紀頃(南北朝時代)
- 構造:標高634mの岩山に築かれた天然の要害
- 特徴:狭い本丸、急峻な尾根づたいに郭が配置され、防御に優れた山城
- 戦国時代:武田家の家臣・小山田氏の居城として拡張
- 本丸から下界を見下ろすと、高さに驚く。登山口からの登山道も急坂が続くので、高度感を強く実感
確認できる遺構

- 本丸の中心にあるこだかい丘部分が放火台跡
- 本丸から「岩殿城跡案内板」方面へ進むと、馬場跡、番所跡、築坂、倉屋敷跡などが点在
武田勝頼の逃亡と岩殿城の悲劇
1582年(天正10年)、織田・徳川の侵攻によって武田家が滅亡の危機に瀕します。武田勝頼は新府城を捨て、家臣の小山田信茂を頼って岩殿城を目指しますが、信茂はまさかの「門前払い」。
行き場を失った勝頼は天目山へと追われ、そこで最期を迎えました。その後、岩殿城も織田軍の攻撃を受けて落城し、小山田信茂も処刑されました。
登山の感想:もう二度と行きたくない?
登山でのハプニング
登山口には「岩殿山で迷わないために」という看板があり、登山用アプリの案内がありました。これのおかげで現在どのあたりにいるのかだいたい把握でき、なんとか生還できたので、インストールすることをおすすめします。
暗くなり、なかなか下山の実感が持てませんでしたが、民家の光が見えた瞬間、涙が出ました。
まとめ:岩殿城を訪れるなら覚悟を!
岩殿城は、武田家の歴史の転換点となった重要な城でありながら、登山としての難易度も相当高い場所でした。もし訪れるなら、しっかりと装備を整え、事前の情報収集を怠らないことをおすすめします。
皆さんも、挑戦する際は十分に気をつけてくださいね!
参考情報:大月市観光協会|岩殿城跡・登山情報